 かーれん
かーれん先日実際に起きた出入国在留管理庁による改善命令のニュースをわかりやすく解説していきます!
はじめに
このブログでは、2025年5月2日付で、お菓子メーカー「シャトレーゼ」の外国人労働者160人に給与未払い、シャトレーゼが入管庁から業務改善命令がありました。
なぜこんなことが起きたのか?を掘り下げて、行政書士の視点で解説していきます!
この記事では、特定技能制度のリスクと、制度を活用する上での注意点がわかる様に解説していきます。
あくまでも制度をよりよくするため、より理解するための深掘りであることを踏まえてお読みください。決して正義の追求!などとは考えておりません。
事件の背景
- 2024年2月以降、5月に発生
- 外国人の労働者の人数:特定技能の在留資格をもつベトナム人157人
- 未払い総額は約4100万円に上る(現在はすでに支払い済み)
- 原因:工事建設の遅延により就労がすぐに不能であったこと
- 結果:出入国在留管理庁から「改善命令」を受けた
そもそも特定技能とは何か?
特定技能制度というのは、外国人に与えられる在留資格のうちのひとつで、
一言で言うと:
人手が足りない仕事を、日本で働きたい外国人に労働してもらうための制度
です。
特定技能には1号と2号に分けられており、次の様な外国人が日本に来て働いています。
| 1号 | 2号 |
|---|---|
| ・一定のスキルと日本語力がある人 ・働ける期間は最大5年 ・家族は連れて来れない | ・もっと熟練した技術を持ってる人 ・期間の制限はない ・家族を日本に呼ぶことができる |
企業の義務としては、
- 外国人とちきんとした雇用契約を結ぶこと
- 日本人と同じレベルの給与を払うこと
- 生活や仕事のサポート(住居、日本語、相談対応など)を行うこと
- 入管庁に報告する書類を定期的に提出すること
があります。
なぜ違反なのか?
このシャトレーゼのケースではなぜ入管庁に違反と判断されたのでしょうか?
ここで挙げられるポイントは、
以上の3つが考えられます。
大きな違反ポイントはやはり休業手当の未払いになりますが、これらの違反は制度全体の信頼を損なう恐れがあります。
もやもや解説
ここでのもやもやポイントをまとめてみます。
①休業手当を払っていない
法的には「会社都合の休業」であれば賃金の6割以上支払い義務があります。
労働基準法
第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
雇用契約を結ぶということは、就労機会の提供が大前提となっており、労働者が日本人であっても外国人であっても休業手当を支払う必要があります。
この視点から見ると、休業手当を払わなかったことで、外国人の労働者を都合のいい単なる労働力=コストとしてしかみていないのか?などとモヤモヤポイントが浮かび上がってきます。
②制度違反ではあるが、悪意はなさそう
新たな工場を稼働するために雇用契約を結んだとあります。
たしかに計画の遅れは”わざと”ではありません。工場建設の遅れは不可抗力になりますが、すでに外国人は労働をするために入国していて、外国人側からすれば経済的に損失があり、なおかつ在留資格の内容にすでに違いがあることから大きなリスクが伴います。
「わざとでなければ仕方ない、問題ない」というような判断でいいのでしょうか?
「違反だったけど仕方がない」というのは制度全体の信頼を壊すことにつながります。
③制度の趣旨と、現場での運用のズレがあった
今回のシャトレーゼの事案に関して、特定技能制度の趣旨と現場での運用のズレが生じてしまったのだと思います。
特定技能制度の目的は、「人手不足が深刻な産業分野において、即戦力として働く外国人を受け入れる」ことであり、適正な在留活動を満たす必要があります。
適切な在留活動というのは以下の通り例を挙げます。
- 契約に基づき、就労していること
- 特定技能雇用契約に基づいた職務内容・勤務地・労働時間で実際に働いている
- 支援体制が整っていること
- 登録支援機関(支援してくれる団体)や所属機関(働く会社)による義務的支援を受けながら、安定して生活・就労している
- 報酬・労働条件が契約通りであること
- 支払いの遅延や未払い、給与手当の不払いは「適正な在留活動」ではない
では、逆に「適正でない在留活動」というのは?
- 就労の実態がない…待機状態、工場未稼働、契約先が稼働不能など
- 契約外の仕事に従事…他部署、他工場、他業務に勝手に配置
- 支援が全く行われていない…生活支援計画が未実施、連絡もない
- 労働条件が契約と異なる…賃金不払いや過度な拘束・残業強要など
これらは在留資格の趣旨に反するため、在留資格取消しの対象となる可能性があります。
このように、制度の趣旨と現場での運用に異なる点があったことから、入管庁による調査で違反が発覚したと思われます。
元もないことを言うようですが、申請書類の雇用条件書に休業手当に関する欄は必ず有りでチェック入れてるはずなんですけどね。(そもそも無しの欄がありません)
実務上の教訓と再発防止策として
この事案から学び、他の特定技能の外国人を採用している企業や人事部が学ぶべき点を整理してみましょう!
「雇用契約=就労開始」の準備が整ってから入国させる
稼働前に入国させると、給与支払い義務が発生します。働けない期間でも契約は有効となります。
「待機状態」でも給与または休業手当の支払い義務がある
会社都合で働かせられない場合でも、労働基準法26条の休業手当が必要になります。
できれば雇用契約に「休業時の給与支給方法」を明記するのが良いでしょう。
登録支援機関に「丸投げ」ではダメ。責任は企業側に残る!
名義貸し的な支援体制では制度違反となります。支援義務は委託しても、企業が最終責任を負うことを認識してください。
支援内容の報告、面談記録、支援実施状況を企業側も必ずレビューをするようにしましょう。また、委託契約書に「不履行時の違約条項や報告義務」を追加するのもいいでしょう。
外国人本人への十分な説明と記録が不可欠
雇用条件や待機理由を本人が理解していないと、トラブルや入管通報の原因になります!
外国人本人が理解できる書面の作成はもちろん、定期面談と通訳を交えた記録の保存がトラブルを回避するポイントです。
支援体制の「現場対応力」が問われます
「働いていない=支援も不要」ではありません。待機中こそ、生活支援が必要になります。
特定技能の義務的な支援には生活に関する支援があります。必ず行わなければならない支援を怠ると、違反として指摘されるのは当然ですよね…
経営層・現場管理者への法令研修が不可欠
「うちはよくわからない」「外国人担当者に任せている」は通用しません!
年に2回以上の入管法・労基法・制度運用研修を管理職に義務付けることや専任の行政書士や社労士による研修動画を依頼したり、社内マニュアルを整備することが再発防止につながります。
おわりに
いかがでしたでしょうか?
特定技能制度は「受け入れればいい」という制度ではありません。
外国人材と企業双方の信頼を守るための運用が必要不可欠です。
特定技能制度をしっかり理解している行政書士に相談をするのも1つのポイントです。
制度を理解した実務運用ができる企業や登録支援機関こそが、これからの特定技能を支える柱になります。
これらの制度について、当オフィスでも相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

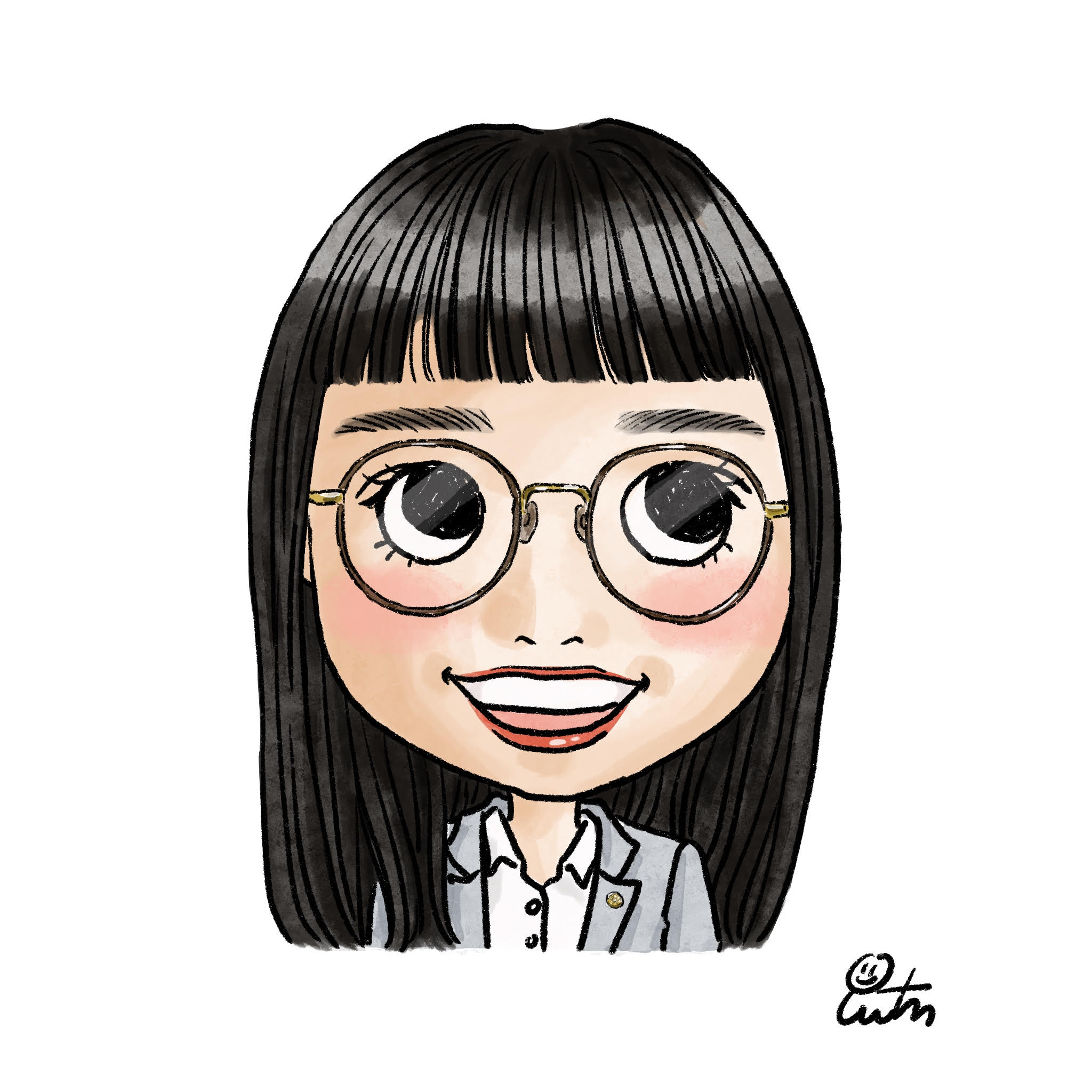
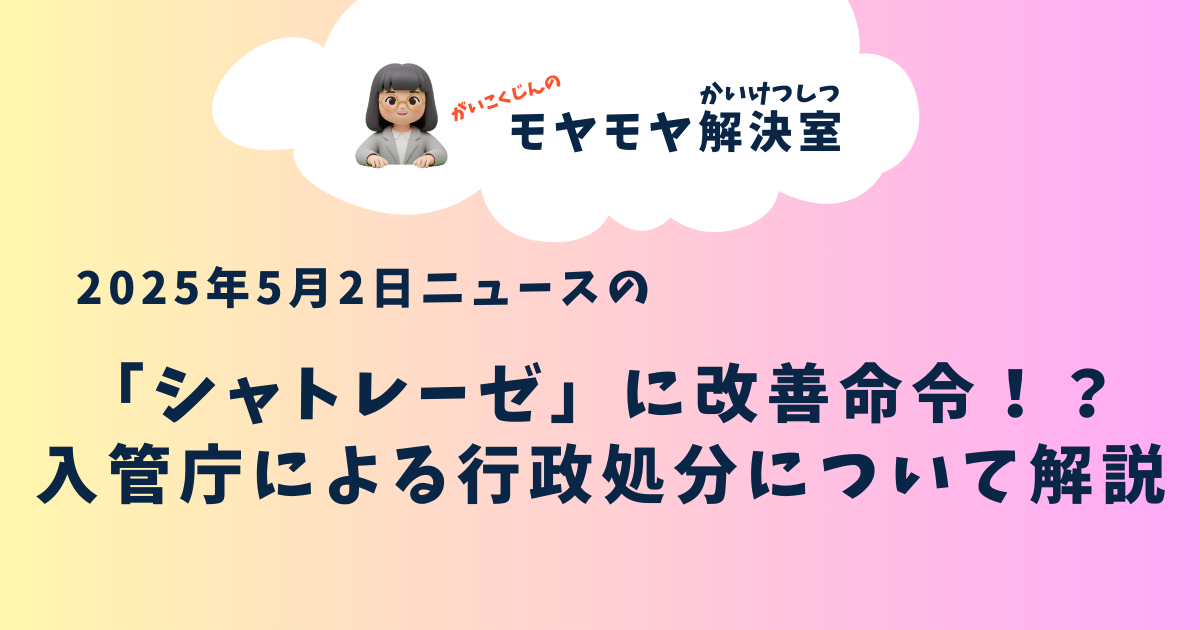
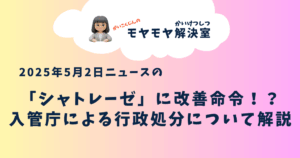






コメント